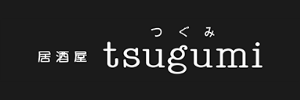【#今治を耕す人】守りたい風景と、続ける現実のあいだで・多伎川圃場
「工業をやりたい」「商業をやりたい」とは言いませんが、「農業をやりたい」という言葉はよく耳にします。それは、農業が単なる職業ではなく、暮らし方や生き方そのものに関わる行為だからかもしれません。かつて、食べものを育て、生み出すことは日常の当たり前でした。しかし、近代化や高齢化の影響で、今治の山あいに広がる里の風景も、少しずつ変わろうとしています。
こうした状況のなかで、今治では農業との向き合い方をあらためて考えようとする動きも生まれています。2024年3月には、市が「オーガニックビレッジ宣言」を行い、受け継がれてきた豊かな土壌を次の世代につないでいこうとする取り組みが始まりました。農業をめぐる選択肢や関わり方も、少しずつ変わりつつあります。
本連載 「#今治を耕す人」 では、地域の風景を守りながら、一次産業に関わる人々にスポットを当て、田んぼや里山といった身近な風景を支える日常や苦労、喜びを追いかけます。
初回に登場するのは、本業のかたわら、4年前に数人のグループで農業を始めた「多伎川圃場」の窪田陽平さん。持続可能な農業の難しさ、支え合う地域のつながり。窪田さんたちの営みを通して、田んぼや里山といった身近な風景をどう守っていけるか、改めて考えるきっかけを届けます。
目次
原風景としての田んぼ
梨の産地として知られる今治市古谷。朝夕の寒暖差が大きく、山から流れ出す多伎川の清らかな水が注ぐ土地の最上流に、窪田陽平さんたちが管理する多伎川圃場が広がっている。

米づくりに携わり、気がつけば4年目を迎えた。
窪田さんの原風景には、いつも田んぼがある。専業農家の祖父母。父親は警察官として働きながら米づくりを手伝い、定年退職後は本格的に米や野菜を育ててきた。日常のすぐそばにあったその姿は、意識せずとも心に残っていたという。
一方で、窪田さん自身は農業とは異なる道を歩んできた。みずほ証券に入社し、名古屋で5年、香川で3年半。金融の世界で経験を積み、証券業の免許を取得して今治に戻り、2015年に独立した。
転機が訪れたのは、知人に誘われて参加した自然栽培の講演会でのことだった。
「米がキロ1,500円で売れる、という話を聞いたんです。」
親の世代を含め、農業に関わる人は高齢化し、耕作放棄地は年々増えていく。その景色を見続けることに、どこか心が引っかかっていた。
コロナ禍の2021年。ちょうど会社を離れ、次の会社を立ち上げるまでの準備期間とも重なった。
「自分でも、やってみようかな。」
そう思えた背景には、身近に頼れる存在があった。
「父が農業をやっていたのは、大きかったですね。分からないことを教えてもらえる人がいる。環境が良かったですね。」

耕作放棄地を再生して初めての米作りへ
窪田さんの農業への思いに賛同したメンバー5人ほどが集まり、2022年から米づくりをスタートさせた。
とはいえ、まずは「開墾」からだった。3月から6月にかけて、耕作放棄地だったおよそ4.5反の土地を、少しずつ圃場へと戻していった。長いあいだ使われていなかった田んぼは、草に覆われ、歩けば芋のつるに足を取られた。
しかしその状態が、かえって幸いした面もあった。数年間放置されていたことで、土に残る農薬は減り、窪田さんは、この土地なら環境負荷の少ない農法が実現できるのではないかと考えた。
「数カ月かけて必死に開墾して、ようやく田植えまでたどり着きました。」
だが現実は想像以上に厳しかった。特に無農薬の田んぼで立ちはだかるのが、雑草だ。田植えが終わると、間を置かずに草が生えてくる。
「最初の1年目は、本当に草取りがきつくて、ひたすらみんなで除草作業に時間を費やしました。」
メンバーそれぞれが10万円ずつ出し合い、除草機も導入。週末ごとに田んぼに出ては、早朝から草と格闘した。
周囲の反応も、決して前向きなものばかりではなかった。父親や近隣の農家からは、「農薬を使わない米作りなんて、大変すぎて、初心者にできるわけがない」と言われることもあったという。
それでも、圃場は山の上流に近く、水が最初に流れ込む場所でもある。
「下流や生きものたち、生態系のことを考えると、やっぱりここでは農薬を使わないほうがいいんじゃないかって。」

そうして収穫を迎えた1年目の秋。思いのほか収量は多かった。
「元々が耕作放棄地だったので、土には養分がたっぷりあったんです。初年度は1,800キロ程のお米を収穫しました。」
無農薬・無肥料にこだわって作ったお米。一方で、農薬や化学肥料を用いる慣行栽培であれば、2,400キロ程度の収穫が見込めるという。
同じ田んぼ、同じ一年。その差は、数字以上に大きい。

続けられる形を探す
翌年は、除草にかかる手間と時間を踏まえ、栽培面積を一部絞って再スタートを切った。
3年目となった昨年からは育苗にも挑戦。無農薬・無肥料で苗を立てつつ、有機JAS認証の肥料も試しながら、少しずつ安定した栽培を目指してきた。今年は省力化を期待して紙マルチを試験的に導入。作業工数は大幅に減ったものの、それでも手ごわい「ヒエ」を完全に抑えることはできなかった。

多伎川圃場を共に耕すメンバーは、入れ替わりを経ながらも現在は5人体制を維持している。全員がそれぞれに本業を持ち、自分なりの思いを胸に農業に関わっている。関わり方も農業との距離感もさまざまだが、共通しているのは「やってみたい」という気持ちだ。
「無農薬だと、味や質にはこだわれますし、自然にもいいと思います。でも、それだけで全部が成り立つかというと、やっぱり限界はあります」
どんな形で届けるのがよいのか。仲間と話し合いながら、何度も考え直してきた。
「無農薬は、たしかに一つの“強み”にはなります。でも、それがすべてじゃない。結局は、食べてくれる人が喜んでくれるかどうかだと思うんです」
立ち上げ当初から関わり、今も活動を続ける白石さんは、ガソリンなどの燃料販売事業を営む自営業の傍ら、「もう一つの軸」として農業に関わりたいと考えたことが参画のきっかけだった。一方で、自然に近い栽培スタイルそのものに関心を持って加わったメンバーもいる。
「ビジネスの視点も踏まえ、ある程度の収量は確保したい」
「無農薬を貫いてきた土壌があるからこそ、簡単には手放したくない」
そんな声が、メンバー同士のあいだでも交わされている。
5年目を迎える来年に向けては、JAS認証の取得を目指して有機栽培を続ける田んぼと、慣行栽培に切り替える田んぼ。その両立を、現実的な選択肢として検討している。

「この田んぼを、なくしたくない」
小規模農家を取り巻く状況は、決して楽観できるものではない。
すべての農家が大きく利益を上げられる構造ではないからこそ、「その地域で続く農業」をどうつくるかが問われている。
「ブランドがあるからいい、というわけでもないと思うんです。
それより何より、農家さんにきちんと買い手がついて、その人が続けていけるかどうか。集落の人たちが食べる米を一手に引き受けるくらいの関係性があって、はじめて成り立つ部分もあると思います」
窪田さんが一貫して大切にしているのは、「地域として農業が続けられるかどうか」。
やり方の正解を探すのではなく、続けられる形を模索し続けることだ。
多伎川圃場は、いまもその模索の途上にある。
「できる範囲で、今やれることを続けるしかないかなと思っています。一つ確かなのは、目の前にあるこの田んぼが耕作放棄地になるのは、どうしても嫌だという気持ちですね」
耕作放棄地をもう一度耕し、作物を育てる場所へと戻していく。
それは景色を取り戻すことでもあり、土地に根づいてきた食の文化を次の世代へ手渡す営みでもある。
一方で、理想だけでは続かない現実があることも、窪田さんは身をもって感じてきた。
「農業だけで食べていけるなら、それもいいと思いますけど、そうもいかない。本業の金融業を軸にしながら、当面は“自分の田んぼを守る”くらいでしょうね。」
父親が借りて耕してきた田んぼも、いずれは返していくことになるだろうと話す。
無理に広げるよりも、いまある田んぼをどう守り、どう続けていくか。
その線引きを、窪田さんたちは日々考え続けている。