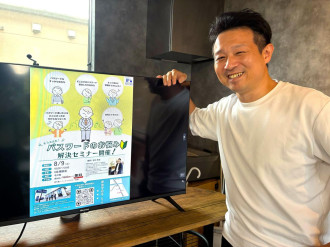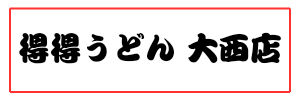故人をしのび、鎮魂の祈りをささげる恒例の「花火供養」が8月18日、城慶寺(今治市湊町2)で開かれた。夜空を彩る108発の花火に、集まったおよそ100人の参拝客や市民が故人への思いをはせた。
[広告]
花火供養は、お盆の「送り」の行事として30年ほど前に現在の丹下甫澄住職が発案したもの。丹下住職によると、江戸時代から行われていた流し灯籠が海上交通の発達により難しくなったため、故人をしのぶ形を花火に変えたのが始まりだという。
当日は朝から300人ほどの檀家が供養に訪れ、祭壇で手を合わせた。花火は、寺の門前にある湊漁港から、毎年、人の煩悩の数とされる108発の3寸玉が夜空に上がる。亡くなって1年を迎える遺族からは故人へのメッセージが、他にも一般の参拝者からも願い事や祈願のメッセージが寄せられ、花火玉に貼り付けられて夜空へと届けられた。
この花火供養、2020年までの約20年間、中止されていた時期がある。丹下住職は「小さい頃に花火供養に参加し、寺で花火を見たと思い出を話してくれた人から『子どもにも見せてあげたい』という声を聞き、再開を考えていた。そうした中、コロナ禍で市内の花火大会『おんまく』が中止になったため、コロナ退散を祈願して復活させた」と話す。
丹下住職は「小さいけれど頭上で上がる花火は迫力があり、音が遅れることもない。花火を楽しみにしてくれているファンのためにも、来年以降も恒例行事として続けていきたい」と意気込む。